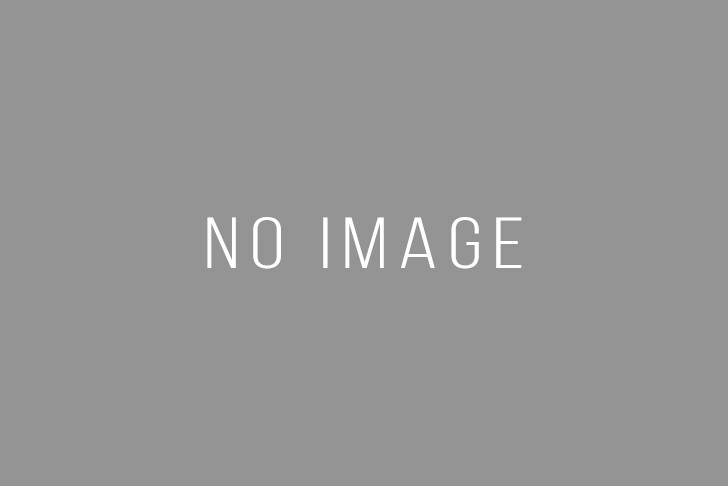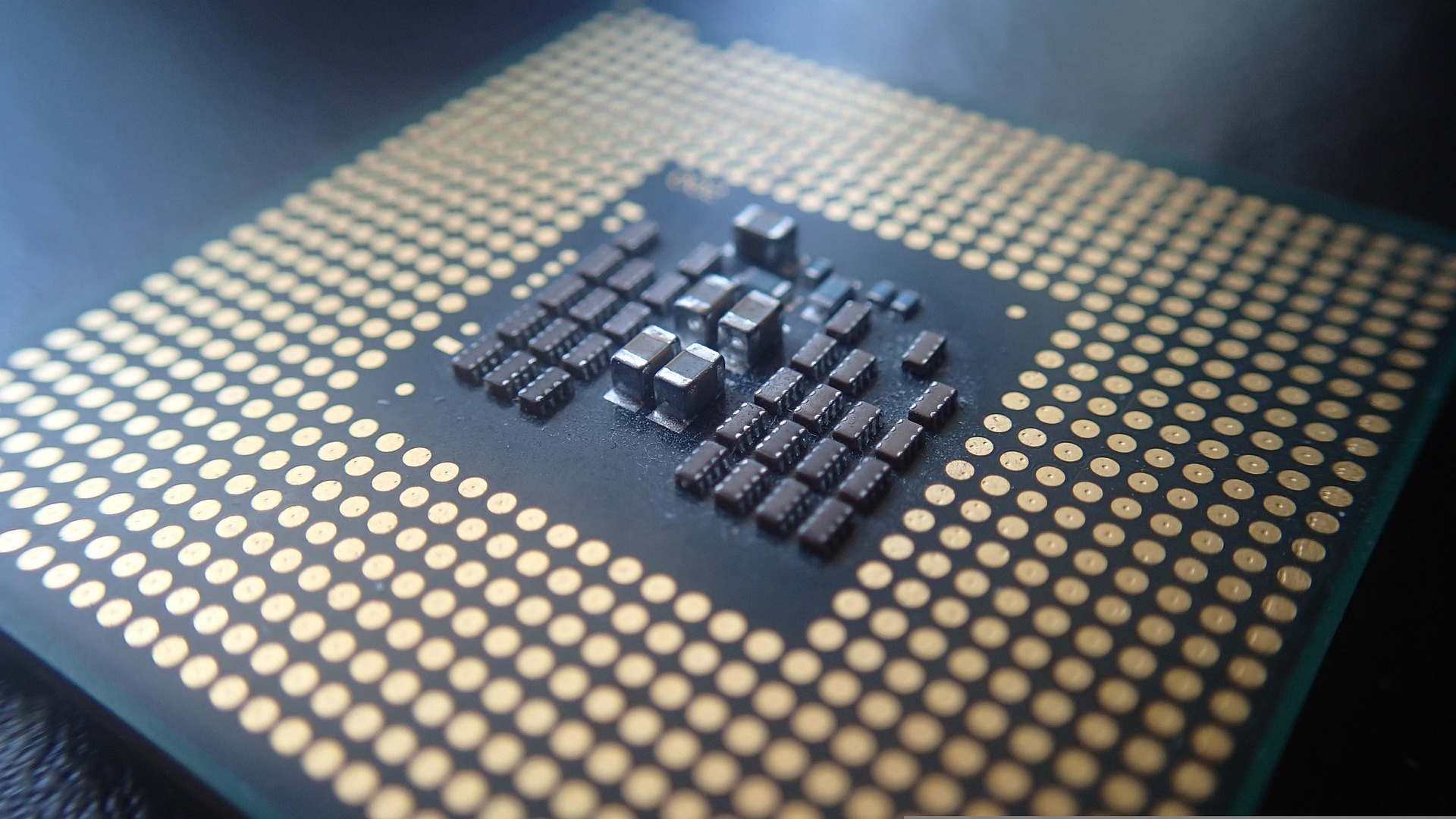大手海外パソコンメーカー一覧【特徴や選び方解説】
パソコンの購入を検討する時に、価格としてどのくらいの物を買えば良いのかという事と同時に、どこのメーカーの製品が良いのか選択に迷う事はないでしょうか。
特に国内メーカーの方が良いのか海外メーカーが良いのか判断が難しいですよね。
これから初めて買うというパソコン初心者の方なのか、ある程度の知識はあって使用用途が決まっていたり、使用頻度や生活環境などによって選ぶべきパソコンは変わってきます。
今回は大手海外パソコンメーカーの一覧という形でまとめてみました。
ぜひパソコン選びの一助として頂けると幸いです。
コンテンツ
海外メーカー製パソコンの特徴
大手海外メーカーのパソコンの特徴は、ずばりコスパ面と言われています。
特にDELLやLenovoと言った海外メーカーはコスパが高く法人でもよく使われています。
また、国内メーカーより初めから入っているアプリが少なかったりサポート体制が弱かったりする代わりにハイスペックなモデルを安価で手に入れる事が出来ます。
少しでもパソコンに慣れている方であれば手厚いアフターケアがなくても十分使えると思いますので、海外メーカー製のパソコンは選択肢として充分視野に入ってくるでしょう。
大手海外パソコンメーカー一覧
| Lenovo | コスパで選ぶならこのメーカー。低価格だが耐久性にも評判あり。 |
| DELL | 安くて使い勝手の良いパソコンはDELLがおすすめ。 |
| hp | デザイン・品質・価格、三拍子揃ったこだわりのある方に是非とも使ってほしいメーカー。 |
| Apple | 洗練されたデザインで飽きのこない使い心地。macOSという独自OSを搭載。 |
| Microsoft | Windowsと親和性が高く初心者からビジネスのシーンまで活躍。 |
| ASUS | パーツメーカー色が強いが、デザイン性と機能性を両立した低価格モデルから高級モデルまで幅広い製品が並んでいる。 |
| MSI | ゲーミングパソコンの代表格。その上薄型・軽量・高性能の三拍子が揃っている。 |
| LG | 韓国の大手家電メーカー。グループ企業が生産したリチウムイオンバッテリーを搭載しているのも特徴でそのバッテリー持ちが評判。 |
| HUAWEI | 中国の電機メーカー。フルビューディスプレイによる画面の広さなどが特徴。 |
| SAMSUNG | スマートフォンなどでもおなじみの韓国最大の電機メーカー。「Galaxy Book」シリーズのノートパソコンやタブレット型PCが知られている。 |
Lenovo
Lenovoは中国のパソコンメーカーで世界シェアでDELLやHPと競い合っており、低価格のビジネスモデル用を中心に販売している。
デザイン面での不評もあったが、最近のモデルでは洗練されたデザインのものも増えている。
価格を重視したメーカーなのでスペック面を重視する方には不向きのメーカーと言える。
DELL
DELLはアメリカのコンピューターテクノロジー企業。
こちらも主にビジネス用のものをメインに販売しているが、ゲーミングパソコンブランドの「エイリアンウェア」も展開しており、ゲームユーザーからも注目されている。
使い勝手も抜群でお手頃価格のものが多く、コストパフォーマンスを重視する方におすすめ。
hp
アメリカの電子機器メーカー。
ノートパソコンの種類も豊富で、小型で持ち運びに便利な製品やおしゃれなデザインが人気。
こちらもコストパフォーマンスに定評があり、近年はゲーミングパソコンにも重きをおいており、ゲームユーザーからの人気も高まっている非常にオールラウンダーなメーカー。
Apple
iPhoneでお馴染みのメーカー。
動画編集、音楽家、デザイナーなど世界中のあらゆるプロが愛用している。
WindowsではなくmacOSという独自のOSを搭載しており、操作性が異なったり、非対応のゲームが多いなど少々使う人を選ぶかもしれない。
価格帯としては高価な部類に入るが、洗練されたデザインと高いマシンパフォーマンスが多くの人を魅了しており、一度Apple製品を使い始めたらずっと使い続ける人も多い。
Microsoft
Microsoftはアメリカのソフトウェアメーカーで、WindowsやOfficeシリーズを開発している。
シーンに合わせて使い分けが可能なノートパソコンとタブレット両方の機能を持つ2in1型「Surface」を主に取り扱っている。
ソフトウェアの開発元なので、OSやパソコンソフトに関するトラブルも少なく、海外メーカーの中では初心者からも人気があるのが特徴。
ASUS
パソコン関連パーツやスマートフォンなどを扱う台湾のメーカー。
世界シェアトップクラスで様々な製品ラインナップがあり、デスクトップ型やノート型・ゲーミングパソコンが豊富に選べる。
デザイン性の高さが魅力で、ゲーミングパソコンにも力を入れており、個人的にイチオシのメーカー。
MSI
台湾に本拠地を置くグローバル企業。
日本国内での人気はそれほど高くないが、世界的に見ると多くのゲーマーに支持されている特にグラフィックボードなどに力を入れているメーカーです。
世界的に見るとMSIのブランド力は圧倒的で2021年の年間売上8,000億円。
ラインナップ数も豊富で選びがいがあり、こだわりのデザインが好みの方にはおすすめです。
LG
韓国に本社を置く家電メーカー。
同社のノートパソコンはLG gramとのLG UltraPCの2種類のブランドを展開しておりどちらにも共通して言えることは軽量で持ち運びに長けておりあらゆるシーンでも重宝するという点です。
スタイリッシュなデザインも好評の理由。
HUAWEI
中華人民共和国の通信機器大手「華為技術」が展開するブランド。
Pocket WiFiなどで有名なメーカーですね。
Windowsを搭載したノートパソコンやモバイルノートパソコンも販売しており、デザイン性や価格性能比に優れている。
また指紋センサーが一体になった電源ボタンや、ポップアップで出てくるカメラなど、面白い仕組みで人気な一方、初期不良があったりパソコンが重いと言ったデメリットも。
SAMSUNG
スマートフォン市場において、世界首位の韓国企業です。
ノートパソコンやタブレット型がある、「Galaxy Book」シリーズのほか、Chromebookなどを展開している。
Galaxy Bookは画質にこだわりたい方に非常におすすめ。
1920×1200の優れた解像度を備えているのと、専用タッチペンが付属しているので、クリエーターにも支持が高い。重ねて約9時間使えるバッテリーも素晴らしい。
タブレットととしては申し分はないがパソコンとしてはシンプルで手頃なものというイメージで少し印象が薄い。
メーカー選びのポイント
それでは実際に購入の際選ぶ時のポイントを見ていきましょう。
ポイント①自分が必要としている性能を満たしているか
各メーカーそれぞれ強みもあるがもちろん弱みもあります。
例えば画質はとびきり綺麗だが、バッテリー持ちが悪いと言う特徴のパソコンは屋外での使用場面が多い方には不向きなものとなりますし、ビジネス向けのパソコンだとゲームをするのに必要なグラフィックボードを搭載しておらずうまく動かないなどの弊害が考えられます。
またAppleのパソコンは他のメーカーとは異なるOSを搭載しており、操作方法が異なっています。
その弱みが自分がパソコンを使用する目的に対して、条件を満たしているか確認しましょう。
ポイント②自分に合ったサポート体制は用意されているか
故障時の無償修理対応の有無や期間、技術的な質問の無償電話サポートの条件など、メーカーによって対応が異なってきますので、自分が必要とする内容を事前に調べる必要があります。
ポイント③見た目が好みであるか
パソコンは高い買い物なので、一度購入したら長く使いたいですよね。
気に入ったデザインなら愛着も湧いてきますので、パソコン選びに迷ったら最後は見た目で決めてしまいましょう!
海外メーカーのデメリットは?
以前は国産メーカーと比べてサポートに難ありと言われていたようですが、現在では改善されてきているようです。
基本的には国内メーカーと同じWindowsがインストールされており、「海外メーカーだから表記が全部英語…」と言う事はないですが、万が一のトラブルの際にサポート対応が悪くて困らないように各メーカーのサポート体制を調べておいた方がいいでしょう。
通常は電話対応を行っているかメールでの問い合わせが多いですが、最近ではチャット形式で対応してくれるメーカーもあります。
またよく比較対象として挙げられる、付属の独自ソフトウェアがあまりないというのはパソコンの初心者にとってはデメリットになるかもしれない、というイメージでしょうか。
購入して電源を入れてすぐに使いたいという方にはありがたいですが、逆に慣れてきて使用するアプリケーションにもこだわり始めた時に、余計なアプリケーションがない分HDD容量も節約できるので逆にメリットに変わる場合もあります。
まとめ:海外メーカー製には国内メーカーには無い魅力がある
国内メーカー製のものは購入後の保証やサポートなどトータル面で安心感があります。
そして大手海外メーカーのものはコスパが良い物が多く、国内メーカーにはない魅力があるのが特徴です。
パソコン初心者で知識やトラブル対応に自信のない方はアフターサービスの優れた国内メーカー製を選択した方良いと思いますが、ある程度の知識をお持ちの方、またはデザイン性やマシンパワーが必要な作業を行いたい方には海外メーカーがおすすめです。
サポート体制にやや不安なところはあるとされますが、電話対応や24時間対応のメーカーも増えてきているので気に入ったものがあればぜひ購入してみてください。
自分の使用用途をしっかりイメージした上で、長く使えるパソコンに出会って欲しいと思います。